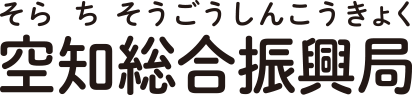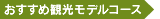
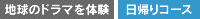
“夕張の顔”が語る地球のドラマ。日帰りドライブで、5000万年前の夕張へ。
 「石炭」は、古代の植物が長い期間、地熱や地圧を受け変質してできた植物の化石。
「石炭」は、古代の植物が長い期間、地熱や地圧を受け変質してできた植物の化石。
はるか4000~5000万年前、夕張一帯はメタセコイアやニレ、カツラがうっそうと茂る湖沼地帯だったという。
“夕張の顔”が語り伝えてくれる地球のドラマから、スタート!
※詳細な地図はこちらをご覧ください。(PDFファイル:423KB)
経路
岩見沢→→  →→丁未峠~→→
→→丁未峠~→→  →→石炭の歴史村→→夕張市内にて昼食→→
→→石炭の歴史村→→夕張市内にて昼食→→  →→市営駐車場前→→
→→市営駐車場前→→  →→レースイスキー場駐車場~冷水山→→
→→レースイスキー場駐車場~冷水山→→  →
→  →→清水沢ダム→→
→→清水沢ダム→→  →→シューパロ湖
→→シューパロ湖
9:00 地層
札幌から高速道央道で岩見沢へ。岩見沢ICで降り、道道38号をひたすら夕張方面へ。40kmほどで、峠を越えると東側の崖に、高さ100m近い地層の露頭が見える。人の顔のようにも見えるので“夕張の顔”と呼ばれているとか(正確な名前の由来は不明)。この地層は、新生代古第三紀の石狩層群。石炭層(夕張炭田)が形成された4000~5000万年前の地層だ。
![]()
9:30 散策
この丘を下れば、「石炭の歴史村」。地球のドラマを体感する、要チェックポイントだ。道道38号、「石炭の歴史村」の北口駐車場では3坑の坑口をすぐ近くに見ることができる。
![]()
10:30 石炭大露頭「夕張24尺層」

本日のハイライトは、ここ。石炭の歴史村内、石炭博物館模擬坑道出口付近にある、北海道指定天然記念物「夕張24尺層」だ。日本の地質百選にも選ばれている。1888(明治21)年に発見された夕張炭鉱発祥の自然モニュメントで、7mもの大きさの石炭層を間近に見られるのは全国でもここだけ。下から10尺層、8尺層、6尺層という厚さの炭層が積み重なっていて、その合計が24尺、つまり7.2m。厚さ1mの炭層ができるためには、植物遺体が17~20mの厚さで堆積する必要があるといわれ、24尺層ともなると、優に100mを超える植物遺体の堆積が必要ということになる。そんなことを思いながら見上げる24尺層の景観は、見事!のひとことに尽きる。
![]()
11:00 夕張市内で昼食
夕張駅すぐそばの屋台村には、ジンギスカンやラーメン、寿司など、北海道のうまいものが集結。ちょっと覗いてみよう。
![]()
12:30 市役所駐車場近く
市役所駐車場の近くの地層に注目。黒っぽい地層が見える。これは石炭層が形成される古第三紀よりさらに古い、恐竜の時代・白亜紀の地層だ。夕張市の西方にある鳩ノ巣山を中心に、白亜紀の地層、それを取り囲むように同心円状に古第三紀の地層が分布。中心部の隆起と激しい浸食により、中心部ほど古い地層が露出している。その形は、ちょうどおわんを伏せたような形をしているので、「ドーム構造」とも呼ばれる。夕張炭田の特徴的な地質構造のひとつであり、「鳩の巣ドーム」として地質学的には有名だという。
![]()
13:30 レースイスキー場駐車場~冷水山
市役所駐車場から南に向かうと、再び古第三紀の地層が現れる。そのひとつがレースイスキー場駐車場から旧道をさがったところにある地層。ここでは、新しい地層の上に古い地層がのっかっている“地層の逆転”を観察できる。激しい地殻の変動によるものだというが、それにしてもこんなに硬い地層がひっくり返るなんて、すごいドラマだ。
時間があったらスキー場の冷水山に登ってみよう。山頂付近のそばで、古第三紀の植物化石が観察できる。
![]()
14:30 清水沢ダム
道道38号を南へ。清水沢で国道452号へ左折、シューパロ湖方面へ向かう途中の「清水沢発電事業所」看板の先で右折すると清水沢ダムが見えてくる。このあたりは古第三紀の幾春別層が露出しており、清水沢ダムもこの硬い幾春別層に地盤を求めてかけられた。ダム直下には、岩肌にはっきりと地層の重なりを見て取れる三角形の奇岩がある。傾斜した地層は夕張川に沈み込み、このまちの地下に展開する“地球のドラマ”に思いを馳せることができる。
![]()
15:00 シューパロ湖

大夕張ダム周辺の道道136号沿いでは、白亜紀の地層が露出している。国道452号へ戻り、シューパロトンネルを抜けるとシューパロ湖。対岸に3段の河岸段丘を望むことができる。この段丘は、地盤の隆起に伴う河川の浸食により形成された、新生代第四紀の地層だ。
“夕張の顔”で古第三紀、市営駐車場付近で白亜紀、レースイスキー場近辺と清水沢ダムで再び古第三紀、シューパロ湖手前で白亜紀へ戻って、湖の対岸に新生代第四紀。夕張のまちを横切りながら、いくつもの時代を行き来した時空の旅。夕張は、奥深い。
(参考文献:改訂版空知の自然を歩く/北海道大学図書刊行会)