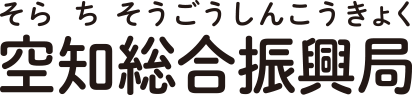稲作体験学習会
南部耕地出張所では、毎年近隣の小学校(継立小学校)の稲作体験学習会を通じ、未来を担う子供達の育成を応援すると共に、農業農村の発展に寄与しています。
田植え(令和6年5月16日)
稲作体験学習のスタートは毎年5月、ゴールデンウィーク明けの田植えから始まります。
汚れてもよい格好で、全員整列!
これは*コロを掛けているところ。農具も少し重い上に田んぼの土の粘性が高いのでとても大変です。
※コロ・・・田んぼに苗を植える印をつける農具。南部耕地出張所ではコロと呼んでいましたが、ころがし、ゴロ、田植枠、枠ころがし、田植定規等、各地で様々な名称や形状(六角形状が多い)があるようです。子供の力では勿論、大人でも真っ直ぐ引くのは難しかったです。
この日のために用意されたたくさんの苗
田植えは機械を使わず、子供達の手作業によって進められていきます。昔は田植えの時期は学校を休みにして、総動員で田植えにあたったとか・・・
腰を曲げての長時間に渡る大変な作業だけに田植機には本当に感謝ですね。
グランドのような大きな田んぼに、学年、班別になって苗を植えていきます。
ここまで来たらゴールは近い?!
田植え終了、真っ直ぐ植えられたかな・・・?
草取り(令和6年7月5日)
草取りは稲の生長を阻害する雑草を取るのが主な作業になりますが、子供達は田んぼの中に生育する様々な生き物に興味津々です。
網を使って田んぼの中の生き物を探します。
アメンボ、ゲンゴロウ、ヤゴ・・・・
一番人気はカエル?
おたまじゃくしからカエルになったばかりですので、まだ小さくて可愛いですね。
捕まえた生き物を使って生態系のお勉強。僕らはみんな生きている・・・♪
稲刈り(令和6年9月10日)
秋に入り、たわわに実った稲を収穫する時期がやって参りました。
先ずは班ごとに作業スペースを割り振ります。
子供達は慣れない鎌を手に稲を刈っていきます。
※周囲の大人は怪我の無いよう安全に気を配っています。
この時、大人はヒヤヒヤ・・・
刈った稲は運んで・・・・
十束程度を目処に縛ります。
そして*はさかけをして・・・・次回以降の学習に続きます!
※はさかけ・・・稲架掛け、はざかけ、はさ掛け、はぜ掛け等々、地域で名称が少々違うようです。刈り取った稲を天日干しにして乾燥させる作業で、お米の水分量を調節したり、ゆっくり乾燥させることでお米の粒を割れにくくする効果があります。また、はさかけによってお米の甘みや旨味が増すという説もあります。
炊飯学習(令和6年11月19日)
みんなで稲刈りした稲を脱穀してお米にしたら、給食にカレーはどうですか?
お米は高学年のみんなが研いでくれて、全校生徒、先生、そして我々で美味しく頂きました。
でも、ごめんなさい。その時の写真はありません。
余りにも美味しくて写真を撮るのを忘れていました・・・・
しめ縄づくり(令和6年11月25日)
稲刈りをしてお米を取られた稲藁ですが、それでお役御免とはなりません。
あんな細い1本の藁を束ねることによって、しめ縄になるのです。
日本の物を無駄にしない伝統文化おそるべし・・・!
えっ?*しめ縄を知らない?ではこちらをご覧下さい。
厳かな雰囲気の中、しめ縄づくりは始まります・・・・
学年毎に別れてしめ縄づくり。
しめ縄づくり中、みんなは何度もこの言葉を唱えます。縄を*なう♪(綯う)・・・・
※綯う・・・糸や藁をより合わせて1本の紐や縄にすること。
説明を聞いても、詳しい作り方が書いてあっても実際の作業は難しいのです。
※しめ縄・・・注連縄とも書き、中国では亡くなった人の魂が再び帰ることのないよう成仏を願って家の前に張る縄だったそうです。日本のしめ縄は日本書紀や古事記によって伝承されてきた天岩戸神話を起源とする説が有力で「しりくめなわ、又はしりくすなわ(尻久米縄)」と呼ばれていたとか。万葉集にも神の存在を表す目印としての「しめなわ(標縄)」や、他にも七五三縄、〆縄という漢字表記もあります。しめ縄、しめ飾りは知っているようで案外知らない世界ですね。
上手く出来たかな・・・?
そして、作ったしめ縄に飾り付けをしていくと・・・・
お正月に飾るしめ縄(しめ飾り)になっていくのです。
令和7年が皆様にとって良い年でありますように・・・