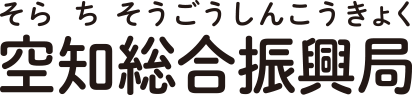英名:melon
学名:Cucumis melo
病害
えそ斑点病
MNSV(メロンネクロティックスポットウイルス)
病原菌名:Melon necrotic spot carmovirus
症状:ウイルスによる病害で葉・茎・果実・根で発生し症状は様々である。
その他特記事項:写真1~8はメロンで発生した症状。
写真:松澤 光弘2003年(写真8枚)

写真1 メロン_えそ斑点病

写真2 メロン_えそ斑点病

写真3 メロン_えそ斑点病

写真4 メロン_えそ斑点病

写真5 メロン_えそ斑点病

写真6 メロン_えそ斑点病

写真7 メロン_えそ斑点病

写真8 メロン_えそ斑点病
バラ色かび病
病原菌名:Trichotheum rosenum
症状:実の花跡に付いて果肉の部分に入る。
対策:玉ふきを丁寧に行うことと、生育後半の急激な水分変化による裂果をさせないこと。
その他特記事項:かびの色が薄紫色をしていることからこの呼び名がある。
このかびに侵された果実は強い苦みがある。
写真:松澤 光弘 2004年(写真2枚)

写真9 メロン_バラ色かび病

写真10 メロン_バラ色かび病
つる割病
病原菌名:Fusarium oxysporum f.sp.melomis(レース1.2y)
症状:初め、葉が肥厚し、光沢を生じる。その後、下位葉から葉全体が黄化するとともに、株全体が萎ちょうし、やがて枯死に至る。地際の茎部が水浸状に褐変し、白いかびが発生することもある。
茎に赤いヤニ状の粘着物をともなう褐色条斑が観察されることもある。茎の導管部は黄変し、根は先端から褐変する。
対策:つる割病抵抗性台木を活用する。土壌消毒を実施する。
写真:松澤 光弘 2004年(写真4枚)
1.jpg)
写真11 メロン_つる割病(R1.2y)
2.jpg)
写真12 メロン_つる割病(R1.2y)
3.jpg)
写真13 メロン_つる割病(R1.2y)
4.jpg)
写真14 メロン_つる割病(R1.2y)
黒かび病
病原菌名:Rhizopus stolonifer(Ehrenberg ex Fr.)Lind
症状:収穫および出荷時には、発病は見られない。龍頭(果更と果実の接点)から黒いカビが生える。
対策:今のところ確立していない。
その他特記事項:本病は、圃場で発病することはない、市場病害※である。(※市場病害:卸売市場、仲卸の段階で発病する病害の総称。ほ場で発病する病害であっても、収穫時に発病が認められず、卸売市場で発病したものは、市場病害と呼ばれる。)
写真:松澤 光弘 2004年(写真1枚)

写真15 メロン_黒かび病
べと病
英名:Downy mildew
病原菌名:Pseudoperonospora cubensis
症状:多湿条件で発生しやすい。
対策:施設内の換気に注意し、薬剤による予防防除や被害茎葉を除去する。
写真:松澤 光弘 2004年(写真2枚)

写真16 メロン_べと病

写真17 メロン_べと病
菌核病
英名:Sclerotinia rot
病原菌名:Sclerotinia sclerotiorum
症状:主に茎、果実侵す。まれに葉を犯すこともある。
茎では被害部は水浸状となり軟化し、のち乾固する。果実は多く花落部から侵され軟腐し、茎、果実とものちに灰白色のカビがはえ黒色の菌核をつくる。
対策:整枝作業などの傷口から侵入することが多ので、作業は天候の良い日に実施する。曇天が続く場合は、作業後早急に予防防除を行う。
その他特記事項:菌核は、低温に遭遇するときのこ状の子のう盤を発芽する。
写真:松澤 光弘 2004年(写真3枚)

写真18 メロン_菌核病

写真19 メロン_菌核病

写真20 メロン_菌核病
害虫
コオロギ
英名:gryllus
学名:Gryllidae
症状:写真のように小指の太さ程度の丸い穴を開ける。加害部位は、花落ち部が主である。これは、皿敷き後、皿の中心部が暗く、生息条件に合っているためと思われる。
その他特記事項:詳細については、未同定であり不明である。
写真:松澤 光弘 2004年(写真3枚)

写真21 メロン_コオロギ

写真22 メロン_コオロギ

写真23 メロン_コオロギ