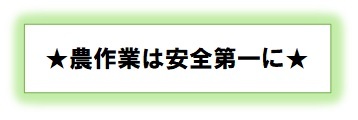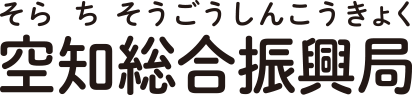対象地域:岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町
・この技術対策は、空知農業改良普及センター本所が所管する地域(岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町)向けに作成されています。
・気象や土壌条件、作業体系などから他地域には適用されませんのでご注意下さい。
全作物共通
①台風や大雨に備え、排水対策やハウスバンドの締め直しなど、風雨に対する備えに努めて下さい。
②ハウスの換気をこまめに行い、適温を確保するとともに、過湿状態が続かないよう注意して下さい。
③今後、最低気温が10℃を下回る日が多くなるので、ハウス栽培では夜間の保温に留意して下さい。
④農薬の使用に当たっては、使用基準を守りましょう。
⑤適期収穫と選別の徹底に努め、出荷物の品質を維持しましょう。
⑥収穫後は有機物の施用など土づくり、排水対策などほ場環境の整備に努めましょう。
ミニトマト
温度管理の目安
・気温の低下とともに、着色の遅れや裂果が増えてきます。夕方は早めにハウスを閉め、夜間の保温に努めましょう。
かん水管理
・裂果が発生しやすくなります。土壌水分やハウス内湿度の変化を小さくしましょう。低温時は保温に努め、かん水を控えましょう。
その他管理作業など
・灰色かび病の発生が多くなります。収穫が終了した花房付近や過繁茂となっている茎葉は晴天日に除去するとともに、発病葉や発病果を取り除き、ハウス外に搬出しましょう。
病害虫、生理障害対策
・灰色かび病の発生が多くなる時期です。換気による除湿、定期的な防除に努めましょう。

写真ミニトマト_古い花弁から発生した灰色かび病
きゅうり
温度管理の目安
・夜温の低下とともに、つるの伸長や果実肥大が緩慢となっています。早めにハウスを閉め保温に努めましょう。
かん水管理
・草勢が低下してくると、曲がり果、尻細果、尻太果が増えてきます。適宜かん水や追肥を行い、果実肥大を促進させましょう。
病害虫、生理障害対策
・病害虫の発生状況に留意し適期に防除しましょう。

写真きゅうり_曲がり果
かぼちゃ
管理作業について
・収穫の目安は花梗部にひびが入り、果皮の表面が硬くなってからです。
・キュアリングは風通しの良い、直射日光の当たらない場所で行いましょう。直射日光に当たると短時間でも日焼け果が発生しやすくなります。
病害虫、生理障害対策
・貯蔵中に腐敗した場合は、つる枯病に罹病していた疑いがあります。次年度に向け、ほ場の排水対策、防除時期の見直し(開花後20日目、30日目)、収穫のタイミング(降雨を避ける)、収穫後の風乾方法の見直し(多湿条件にしない、差圧通風を行う)等に努めましょう。

写真かぼちゃ_つる枯病の様子
夏秋いちご
温度管理の目安
・気温低下により、種浮き果や果皮割れ果などが発生しやすくなります。
・培地の温度は15~20℃を確保し、適切な追肥や葉面散布を行い、草勢を維持しましょう。
かん水管理
・高設栽培の場合は培地が乾燥・過湿にならないよう、排液のEC値を参考に、天候に合わせて給液回数をコントロールしましょう。
その他管理作業など
・葉かきは、古葉や重なった葉、ハダニ類等の被害葉を中心に行い、群落内の通気性を良好に保ちましょう。
病害虫、生理障害対策
・ハダニ類、アザミウマ類の発生が見られる場合、防除を行い、葉、果実を健全に保ちましょう。
・うどんこ病や灰色かび病が発生しやすい時期です。葉かきや循環扇の活用、脱落した花弁や枯葉の除去、薬剤による予防防除を実施しましょう。

写真いちご果実における灰色かび病の様子
アスパラガス
温度管理の目安
・茎葉の伸長適温は気温20~25℃、地温15~20℃と言われています。ハウス立茎栽培では、9月下旬まで温度の確保に努めましょう。
かん水管理
・来春の収穫量を確保するためにも、かん水の管理は出来るだけ長期間行いましょう。
その他作業など
・次年度の養分を貯蔵根へ移動させるため、9月下旬からはハウス側窓を開放し、寒気に当てます。茎葉が80%程度黄変したら地際から刈り取り、残さは、ほ場外へ搬出しましょう。
病害虫、生理障害対策
・茎葉の養分を効率よく根に転流させ、来春の収量を確保するため、斑点病、茎枯病の防除を実施しましょう。

写真アスパラガス斑点病の様子
花き
温度管理の目安
・9月中旬を過ぎると、日によっては生育適温を下回ります。品目により、ハウスをこまめに開閉し温度管理を徹底しましょう。
・適夜温例:
SPカーネーション 10~12℃
スターチスシヌアータ 8~10℃
オリエンタルユリ 15~18℃
・加温作型では、加温機等の点検整備を早めに行いましょう。
その他作業など
・他の農作業と重なる時期ですが、適期収穫を目指し収穫遅れや切り残しのないようにしましょう。
病害虫、生理障害対策
・ほ場観察を行い、アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類、オオタバコガの発生が見られる場合は、防除を実施しましょう。
・気温の低下にともない、施設内を保温するため多湿となります。灰色かび病などの病害が発生しやすくなるので、除湿管理を心がけるとともに、殺菌剤でのローテーション防除を行いましょう。

写真カーネーション_オオタバコガによる食害
写真カーネーション_アザミウマ類による食害痕

写真スターチスシヌアータ_灰色かび病による被害