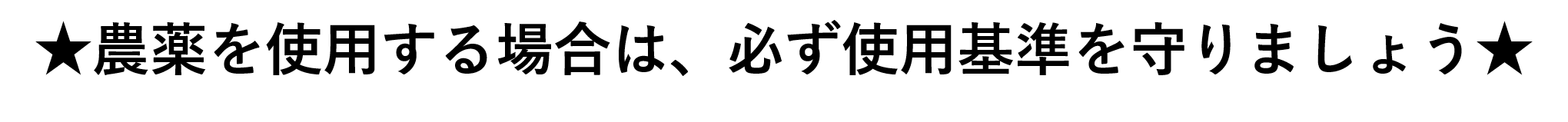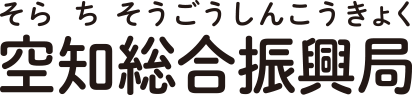対象地域:岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町
・この技術対策は、空知農業改良普及センター本所が所管する地域(岩見沢市、三笠市、美唄市、月形町)向けに作成されています。
・気象や土壌条件、作業体系などから他地域には適用されませんのでご注意下さい。
全作物共通
①ほ場が過湿な状態で、無理に機械作業を行うと、土壌の透排水性が悪化し、生育不良の要因となります。砕土性を高めるため、耕起作業は土壌水分が適正な状態で行いましょう。
②耕起前のパラソイラ、サブソイラ等を用いた心土破砕処理は排水性向上に有効です。
③ほ場準備が遅れた場合は、苗の馴化や適切な管理により老化苗にならないようにしましょう。
④ハウス栽培やトンネル栽培では、気温の日較差が極めて大きい時期なので温度管理に注意を払いましょう。曇天後のわずかな日照でもハウス内温度は、急上昇するのでこまめな管理が必要です。
メロン
温度管理の目安
・最高気温30℃以下、地温18℃以上確保します。
・開花7日前~着果期・ネット形成期は、最低気温15℃程度(活着後12℃程度)を確保し、やや高めの温度管理で雌花を充実させます。
・着果後果実肥大期は、最低気温をやや高め(15~18℃)にし、初期肥大を促します。
・かん水管理
・マルチ下の土壌水分を確認しながら、少量かん水をこまめに実施しましょう。本葉10枚頃に草勢が弱い場合、着果7~10日前頃のかん水が雌花の充実につながります。
・5月下旬に縦ネット期(果実肥大期)に入る作型では、かん水を控えなければならないので、事前にやや多めのかん水を行いベッド内の水むらを解消しておきましょう。
病害虫、生理障害対策
・乾燥状態が続くとハダニの発生が予想されます。発生状況に留意しましょう。

写真 メロン_ハダニによる被害葉
ミニトマト
温度管理の目安
・昼夜の温度差が大きい時期です。日中の気温25℃、最低気温12℃以上を目標に、こまめな温度管理を行いましょう。
かん水管理
・かん水はマルチ下の土壌水分を確認し、生育状況に応じて少量のかん水をこまめに実施しましょう。
その他作業など
・ホルモン処理は日中を避け、涼しい時間帯に行って下さい。(高温時は、奇形果の発生原因になります。)
・わき芽の除去など整枝作業は、晴天日の午前中に行い、傷口が午後には乾くようにしましょう。
病害虫、生理障害対策
・多湿条件が続くと灰色かび病が発生しやすくなります。こまめな換気を行うとともに、発生前に予防剤による防除を行うことが効果的です。

写真 ミニトマト_灰色かび病
きゅうり
温度管理の目安
・ハウス内の温度が急激に上昇したり、湿度が急激に下がったりした場合、生長点が損傷する恐れがあります。急激な換気は避け徐々に換気を行いましょう。日中25℃、最低気温15℃以上を目標に管理しましょう。
かん水管理
・かん水は、土壌水分と生育状況に応じて行いましょう。
その他作業など
・葉色が淡い場合は、葉面散布を行いましょう。
病害虫、生理障害対策
・ハウス内が過湿状態の場合は、べと病などが発生しやすく、乾燥状態の場合は、ハダニが発生しやすくなりますので、発生状況に留意しましょう。
かぼちゃ
育苗における温度管理の目安
・育苗前半は、夜温を15℃以上確保するように保温しましょう。定植期に向けて徐々に管理温度を下げるよう管理し、定植の7日前から外気に馴らしましょう。
セル育苗
・72穴セルトレイの場合、育苗日数の目安は14日程度となります。老化苗にならないよう、計画的には種作業を進めましょう
定植に向けて
・定植1週間前にはマルチ張りなど本畑の準備をし、地温15℃を確保しましょう。
・かん水は定植前日に十分に行いましょう。
・定植は、植え傷みを防ぐため暖かい時間帯に行いましょう。植え込みの深さに注意し、根鉢を壊さないように植えます。植穴と根鉢の間に隙間があると活着不良となるため注意しましょう。
いちご
温度管理の目安
・日中の温度管理は、20℃前後を目標にしましょう。また、30℃以上の高温になると生育が抑制されるため、注意しましょう。
かん水管理
・乾燥、過湿に弱い作物です。朝の葉つゆの状況を見ながらかん水を行いましょう。
その他作業など
・夏秋どり(四季成り)いちごは株を養成するため、花房上げまでランナーと花房の除去を行いましょう。
・高設栽培では、給液、排液のEC を測定して、生育ステージに応じて養液濃度を調整しましょう。
病害虫、生理障害対策
・ハウス内の換気をこまめに行い、枯葉や病果を早めに取り除き、灰色かび病、うどんこ病の発生を抑制しましょう。特に灰色かび病ではジカルボキシイミド系薬剤の耐性菌が確認されているため、使用薬剤の選択に注意しましょう。
・ハウス周辺の雑草が繁茂すると、ハダニ、アブラムシ、アザミウマ類の発生が増加するため、ハウス内及びほ場周辺の雑草除去と観察による適期薬剤散布に努めましょう。
たまねぎ
・生育が停滞しているほ場やクラストの解消されていないほ場では、中耕を実施し生育促進を図りましょう。
病害虫、生理障害対策
・ネギハモグリバエの成虫は例年5月下旬、アザミウマ類は6月上中旬から発生が見られます。発生状況を確認し、薬剤防除を実施しましょう。

写真 たまねぎ_ネギハモグリバエ成虫食痕
アスパラガス
かん水管理
・施設内は乾燥傾向です。かん水量が不足しないように注意しましょう。
その他作業など
・ハウス栽培では、春芽収穫開始約30日後から立茎を行います。立茎の開始は、収穫量、萌芽数の減少、扁平、曲がり、細い若茎が増えてきた頃等を目安にします。
・立茎候補枝を選ぶときは、茎径10~12mmを目安に1株あたり4~5本又は畦1m当たり12~15本を目安としましょう。立茎開始後も立茎枝以外は収穫します。
病害虫、生理障害対策
・ジュウシホシクビナガハムシの成虫は気温15℃以上で活発に飛び回り飛来するようになります。また、アザミウマ類は例年5月下旬頃から発生します。各種害虫の発生に注意し薬剤防除を実施しましょう。
スターチスシヌアータ
温度管理の目安
・ハウス内の温度変化が激しい時期です。晴天時の日中は高温とならないよう注意し、雨天や曇天日は湿度の上昇に注意し換気しましょう。活着後の目標管理温度は、10~15℃です。
その他作業など
・摘心は、活着後、抽台茎が20㎝位になったら1回目を実施します。
・株の直径が40~50㎝(隣の葉と重なる程度)になるまで、摘心します。
・株が十分充実したら(定植後約45日で葉数45枚が目安)、出荷時期を考慮しながら、摘心を止めて抽台茎を立て始めます(最終摘心から採花までの目安:30~40日)。
病害虫、生理障害対策
・摘心や摘葉など作物を傷つけた作業の後は、灰色かび病の予防防除を実施しましょう。
写真 スターチスシヌアータ_灰色かび病による被害